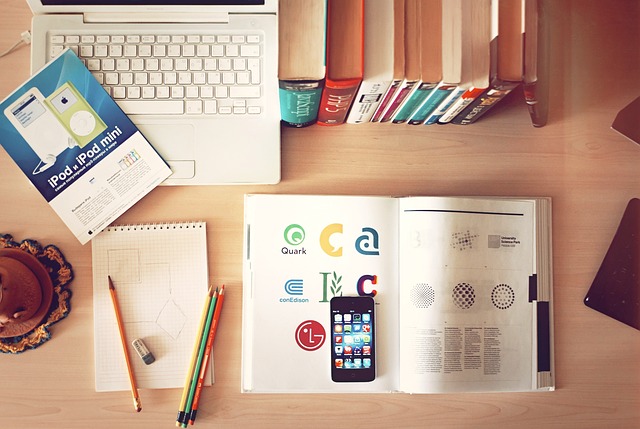工業高校の機械科では、さまざまな資格を取得することができます。
しかし、高校3年間という限られた時間の中で
「一体どの資格を取ればいいんだ?」
と悩んでしまいますよね。
資格取得には「学力・時間・お金」が必要となるので、手当たり次第全てを取得するというわけには行きません。
そこでこの記事では、「就職することを目標にして、機械科ではどんな資格を取得すればいいか」についてご紹介していきます。
資格の中には、簡単に取得できるものもありますが、せっかく取った資格が実は就職では特に有利にならないものもあります。
そのため、高校3年間の時間を無駄にしてしまわないためにも、就職で有利になるためにも、効率的に資格を取っていきましょう。
機械科のおすすめの資格5選

機械科では幅広い分野の勉強を行うので、取得できる資格もたくさんあります。
また、専門分野ではなく一般教科の資格である漢検や英検・TOEICなどの資格もありますが、今回は機械科ならではの資格のみに絞って紹介していきますね。
せっかく機械科に入学したのであればその環境を活かせる資格を取得しましょう。
危険物取扱者
工業高校に入ったのであれば、危険物取扱者の資格取得はある意味ステータスになっている部分があります。
学校や学科によってはこの資格を取得することを推奨していたり、クラス全員が受ける事になっているなんてところもあるくらいです。
この資格は名前の通り危険物を取り扱う免許で、種類によって取り扱えるものが変わります。
一般的なのは乙種4類の資格取得です。
この資格は身の回りにある危険物の全般を取り扱うことができますし、ガソリンスタンドで働けるようになるということで有名です。
危険物取扱者の資格は、全ての種類を取得する必要は無いのですが、乙種4類は基本的なものとして受験する人が多いのです。
アーク溶接、ガス溶接
溶接の世界でも基本となるアーク溶接とガス溶接は、工業高校生にはぜひとも取得してほしい資格の一つです。
溶接は機械科の授業で習い、実習で取り扱ったりすることもありますが、仕事として溶接を取り扱う場合には免許が必要となります。
各溶接の資格を持っていれば金属製品を取り扱う工場や整備工場、建設現場、解体現場など幅広い場面で活躍できます。
2つともあまり難易度も高くないので高校生のうちに取っておいて損はない資格です。
ボイラー技師
ボイラーの操作や点検、整備を行うための資格です。
商業施設などでは必ずボイラーがあり、経営にも重要な設備ですので、ボイラー技師はいつでも必要とされる職業です。
資格取得には段階を踏んで級を上げていく必要があるので、高校生の内に基本の二級の資格を取得して、卒業後に実務経験を積んだら一級や特級の試験に挑戦しましょう。
CAD検定
CADとは設計に関するコンピューターソフトで、工業高校に入れば必ず一度は使用するソフトです。
CADは工業系の会社では基本的なシステムとなっており、研究開発や設計職では使えて当たり前というレベルのものなのです。
CAD検定を持っておけば就職のときだけでなく、転職時などにも有利となります。
また、建築土木、機械、林産など、どんな分野でも活用できるので重宝されるでしょう。
機械加工技能検定
機械を使って金属を加工技術を証明するための資格です。
国家資格であり、さらに名称独占資格であるため、その資格を取得していないと名乗ることができないという重要な資格なのです。
使用する機械や工法によって種類が変わり、分野がかなり細分化されていますので、学校によっては一部の種類だけしか受けられないという制限があったりします。
また、3級は実務経験6ヶ月以上で受験資格が得られますが、2級は2年以上、1級は7年以上、特級は1級を合格してさらに5年以上の実務経験が必要となり、積み上げてきた実力で取得できる資格となります。
機械科なら「CAD検定」は必ず取得しておこう!

機械科に入学したのであればぜひ「CAD検定」の取得を目標にしてください。
CADは多くの分野で活用されているソフトですので、CAD検定を持っていれば就職・転職の際に有利となります。
また、個人で会社やプロジェクトを立ち上げたい時にもCADを使いこなすことができれば便利でしょう。
CAD検定とは?
CAD検定は「CAD利用技術者試験」が正式名称で、CADを使った技術力の保有を証明するための資格です。
CAD検定には「利用技術者試験」と「建築CAD検定試験」が存在し、建築CADは文字通り建築関係で図面などを作成するときに使われる検定です。
機械科であれば利用技術者試験が基本となります。
試験は2Dと呼ばれる二次元部門と、3Dと呼ばれる三次元部門の試験に分かれており、それぞれにも計8種類があります。
2D部門は平面の図面やアセンブリ(組立図)を作成する能力が求められ、その中でも基礎・2級・1級の機械、建築、トレースに分かれています。
3D部門は縦・横・奥行きの3つの視点で作図を行います。
立体的という方が想像しやすいでしょう。
3Dの試験は2級・準1級・1級の三種類で、モデリングやシステム構成、空間把握、2D図面を3D図面に書き直す能力など難易度の高い技術が求められます。
CAD検定は難しい?
CAD検定はどの種類であっても毎回試験問題がガラッと変わるので、基本的なシステムの理解とその応用力をしっかり身につけておかないとかなり難しい試験となります。
逆を返せば基礎をきちんと理解して図面を作り慣れることができれば、低い級なら簡単に合格できる試験でもあります。
実際、親がCADを使った仕事をしており、中学生の頃からCADを教えてもらっていたという高校生は難なく合格する事ができているので、やはり経験値が重要となる試験なのです。
CAD検定を取っておいたほうがいい理由
CAD検定を進める理由は3つあります。
一つは冒頭でも話した通り、CADは幅広い分野で使用されるソフトなので、この検定を持っておけば就職にも有利となるということです。
二つ目は、学校でCAD検定の勉強をする場合、過去問題や練習問題などを本番形式で行う事ができるので、身につく練習が可能になるということです。
自宅で独学で行う場合、問題集などにもお金がかかってしまいますし、一人で模擬試験を行っても緊張感がありません。
しかし学校では他の生徒と一緒に模擬試験を行い、先生が監督役をするので緊張感を持って作業することができます。
これは大きなメリットで、試験本番のときに落ち着いて作業をすることにも繋がります。
三つ目は費用の問題です。
社会人になって独学でCAD検定を取得する場合、まずはCADのソフトを購入しなければいけません。
ソフトの値段が10万円前後します。
また、CADを使いこなすためには高いスペックのパソコンを使う必要があり、場合によってはパソコンの買い替えから始まる場合もあります。
さらに問題集や使い方の参考書などもお金がかかりますので、かなりの出費になることがわかります。
一方学校でCAD検定を取得する場合、学校のパソコンにはCADのソフトがあらかじめ入っており、パソコンのスペックも十分です。
学校の備品ですので許可を取れば無料で使用することができます。
問題集のテキストなどは実費で購入する必要もあるかもしれませんが、学校によっては貸し出してくれますので、実質的には受験費用だけで検定を受けることができるのです。
費用もかからず、さらに教師から直接教えてもらう事ができる上に緊張感のある模擬試験を行える、という環境はCAD検定を取るためにおすすめです。
資格は3つあれば就職試験では十分である理由

工業高校に入ると多くの資格試験の話題が耳に入ってくるでしょう。
先生から誘われたり、ポスターを貼ってあったり、先輩から話を聞いたりと驚くほど資格の話でもちきりになります。
特に部活動に入っていると、先輩が就職活動を行う際に「この資格は取ったほうがいい」と言ったアドバイスをされるので、あれもこれもと取りたくなってしまいます。
しかし、実際のところ就職に関しては3つほどの資格を持っていれば十分です。
資格は成績につながらない
どんなに多くの資格を取得したとしても、それが成績につながる事はありません。
高校生の中には資格取得の方に力を入れてしまって基本教科の成績が落ちてしまったという例もめずらしくないのです。
実際就職の場面になると評価対象になるのは基本教科であって、資格の数ではありません。
もちろん資格を持っている事で優遇される職業もありますが、必ずしも資格を取ることはないと心得ておきましょう。
また、就職の求人は成績の高い人から順にいい企業を希望することができます。
一番良いのは学校の成績も良く、資格を持っていることではありますが、資格は雇用条件に入っていない限りそれほど重要視される項目ではありませんので、まずは成績アップを目指しましょう。
就職後取れる資格もある
工業高校ではなぜかフォークリフトの免許や危険物の資格を取得させたがる傾向にあります。
しかしこれらの資格は、就職後も働きながら取得することが可能ですし、会社によっては資格取得の費用を持ってくれるところもあります。
そのため学生の内に取っておくメリットが大きい資格以外は、就職後にゆっくり取ることをおすすめします。
最後までお読み頂きありがとうございました。